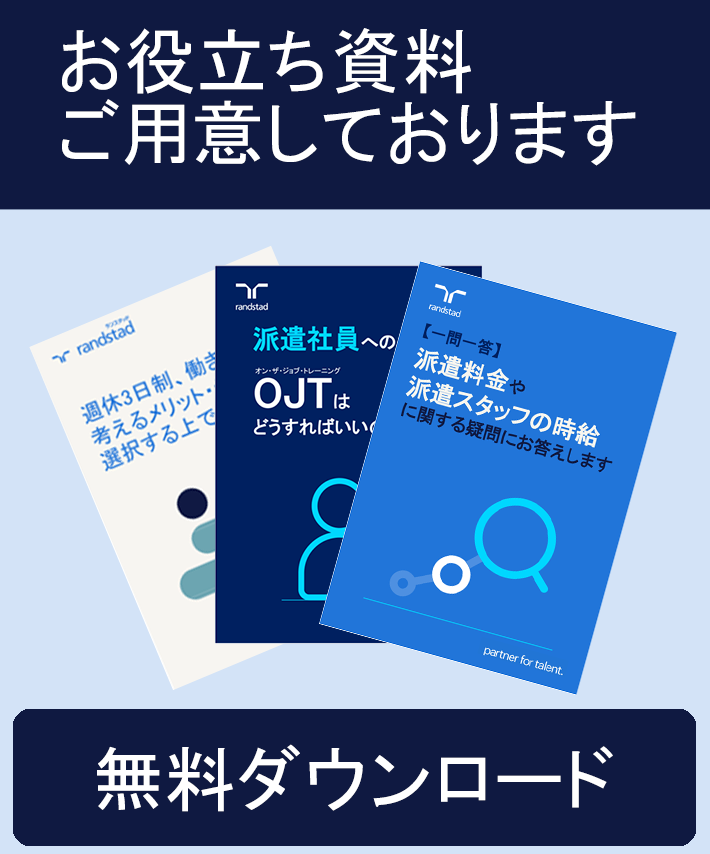- 総合人材サービス ランスタッドTOP
- 法人向けHRブログ workforce Biz
- 社労士のアドバイス/出向者の社会保険、労働保険の適用について
社労士のアドバイス/出向者の社会保険、労働保険の適用について


こんにちは、社会保険労務士法人大野事務所の高田と申します。
弊事務所では、人事・労務分野における様々なサービスをご提供しております。筆者自身も主に労務相談顧問という形で日頃から顧問先企業様のご相談等に対応していますが、本コラムでは、企業で人事・労務の実務に携わる皆様の視点に立って、分かりやすい解説を心がけていきたいと思います。
Index |
ポイント
|
はじめに
企業では、さまざまな理由から自社の従業員を他社に出向させることがあります。この場合に、給与は出向元、出向先のいずれから支給するのがよいのか、また社会保険や労働保険の適用関係はどのようになるのかといった点について、取り扱いを迷われるご担当者の方は多いのではないかと思います。
今回は、出向者の給与と社会保険、労働保険の適用の関係について、一般的な考え方を解説します。
![]()
1.出向の形態について
まず、出向の形態としては、大きく「在籍出向」と「移籍出向」の2パターンに分かれます。
① 在籍出向
在籍出向というのは、出向元の従業員身分を残したまま出向先へ出向する形態であり、労働契約の多くの部分が出向元に残存している関係で、出向元の就業規則の適用を受ける場面の多い出向形態だといえます。したがって、給与についても、必然的に出向元が支払っているケースが一般的(※)です。
※出向者に対して給与を直接支払うのは出向元であったとしても、実質的に負担すべきであるのは労務の提供を受けている出向先であることから、出向先は出向元に対して人件費相当額を出向料として支払います。
② 移籍出向
他方の移籍出向というのは、出向元の従業員身分を残さずに出向先へ出向する形態であり、したがって、労働契約のすべてを出向先に移管することになります。これを出向と称するのは、出向期間終了後に出向元への帰任が予定されているためであり、出向期間中は、いわゆる他社への転職と殆ど違いがありません。勿論、給与についても、出向先が支払うことになります。
③ 兼務出向
「在籍」「移籍」という概念とは切り口が異なりますが、もう1つ兼務出向というものを挙げておきます。
①在籍出向と②移籍出向は、基本的に労務の提供は出向先において行われることを前提としていますが、兼務出向というのは、出向元と出向先のそれぞれに対して一定割合ずつ労務の提供が行われる出向の形態です。
このような兼務出向は、出向元と出向先との間で業務従事割合の調整が比較的容易に図りやすいグループ会社間において、しばしば見受けられます。給与については、出向先における労務提供分を含めて出向元が支払っているケース(出向先は兼務分を出向料として負担する)が多いのですが、出向元と出向先のそれぞれが兼務分に応じて直接出向者に支払うケースもあります。
ここからは社会保険や労働保険の適用をどうすべきかを見ていきますが、以上を踏まえ、①在籍出向の場合は出向元が、②移籍出向の場合は出向先が、③兼務出向の場合は出向元と出向先のそれぞれが、出向者に対して給与を支払っているという前提で説明を進めていきます。
![]()
2.社会保険の適用について
ここでいう社会保険というのは、健康保険と厚生年金保険のことです。適用に関する考え方は両者ともまったく同一ですので、ここでは両者を合わせて社会保険として説明します。
社会保険の被保険者は、「適用事業所に常用的に使用される者」ということになりますが、常用的使用関係にあるのかどうかを判断する上では、労務の実態の他に給与を恒常的に支給しているかどうかがポイントになります。
つまり、給与を直接支払っている場合には被保険者となる一方、給与を支払っていない場合には被保険者になりません。
以上を踏まえると、出向元が給与を支払う在籍出向の場合は出向元で、出向先が給与を支払う移籍出向の場合は出向先で、それぞれ社会保険の適用を受けることになります。
兼務出向の場合でも考え方は同様ですので、出向元が一旦給与の全額を支払っている場合には、社会保険は出向元での適用を受けます。一方、出向元と出向先とがそれぞれの兼務割合に応じて給与を支払っている場合は、どのようになるのでしょうか?
![]()
3.二以上事業所勤務に該当するか否かについて
社会保険の適用の要否を判断する際に、いわゆる「4分の3基準」というものがあります。これは、パートタイマーなど、その事業所におけるフルタイム労働者と比べて労働時間が短い者であっても、「1週の所定労働時間および1月の所定労働日数が通常の労働者の4分の3以上」である場合には、社会保険の被保険者となるというものです。
また、特定適用事業所の場合には、上記の「4分の3基準」を満たさない場合であっても、以下の(ア)~(ウ)をすべて満たす場合には、被保険者になります。これを「短時間労働者の要件」と呼ぶことにします。
| (ア)週の所定労働時間が20時間以上あること (イ)所定内賃金が月額8.8万円以上であること (ウ)学生でないこと |
兼務出向の場合において出向元と出向先とがそれぞれ給与を支払うケースでは、本来は、出向元と出向先それぞれにおいて上記の「4分の3基準」や「短時間労働者の要件」に当てはめて、社会保険の適用の要否を判断することになります。
その結果、両者ともに被保険者になる場合は二以上事業所勤務に該当することになり、それ以外は、いずれか一方でのみ被保険者となるか、あるいはいずれとも被保険者とならないとの結論になるはずです。
ところが、実務的には、上記とは異なる取り扱いをするのが一般的となっています。
たとえば、出向元と出向先での兼務割合が3:2になり、1週間の所定労働時間が24時間:16時間になったとします。この場合、1週間の所定労働時間が16時間である出向先では被保険者になりませんので、出向元でのみ社会保険の適用を継続することになりますが、出向元での給与が5分の3程度に減ると、社会保険の標準報酬月額が大幅に下がってしまうなどの影響を受けることになります。
また、別の例として、出向前の1週間の所定労働時間が40時間に満たない企業においては、出向元と出向先での兼務割合が1:1となって、1週間の所定労働時間がいずれも20時間を下回ると、いずれにおいても被保険者にならず、兼務出向を機に社会保険の加入から外れることになってしまいます。
以上のような事態を避けるために、兼務出向のケースで出向元と出向先のそれぞれから給与が支払われる場合には、「4分の3基準」や「短時間労働者の要件」を満たしているかどうかにかかわらず、両者での社会保険の適用を認めて二以上事業所勤務として取り扱うことが一般的に見受けられるようです。ただし、この取り扱いについては法令や通達等に根拠があるわけではありませんので、個別のケースごとに管轄保険者の判断に委ねることとなります。
![]()
4.労災保険の適用について
労災保険には被保険者の概念はなく、実際に労務の提供を受けた側が、当該労務に相応する給与を基礎として労災保険料を負担するのが原則です。したがって、出向者に対して給与を支払うのが、出向元、出向先のいずれであったとしても、労務の提供先である出向先が労災保険料を負担することになります。
そうすると、兼務出向の場合においても、給与をいずれが支払っているのかにかかわらず、兼務割合に応じて給与を按分して労災保険料を負担するのが妥当だといえます。たとえば、出向元と出向先とが兼務割合に応じてそれぞれ給与を支払っている場合は、それぞれが支払っている給与が労災保険料の算定基礎額になりますし、仮にいずれか一方が給与の全額を一旦支払っている場合であっても、兼務割合に応じた労災保険料をそれぞれが負担するのが妥当だということです。
![]()
5.雇用保険の適用について
雇用保険は、2つ以上の企業と雇用関係を持つ労働者であっても、当該労働者が生計を維持するのに必要な主たる賃金を受けている方の雇用関係についてのみ、被保険者となります(社会保険のような二以上事業所勤務といった概念はありません)。したがって、出向元が給与を支払う在籍出向の場合は出向元で、出向先が給与を支払う移籍出向の場合は出向先で、それぞれ雇用保険の適用を受けることになります。
また、兼務出向において出向元と出向先とがそれぞれ給与を支払う場合は、給与額の多いいずれか一方でのみ雇用保険に加入することになります。そうすると、出向期間中に育児、介護等の給付や離職して失業給付を受けることになった場合は、現に加入しているいずれか一方の給与額のみが給付の基礎となります。
![]()
まとめ
以上のとおり、出向時における社会保険や労働保険の適用は、出向元と出向先のいずれが給与を支払っているのかによって、取り扱いが大きく左右されます。
本コラムでは、兼務出向の場合には、出向元と出向先の両方が兼務割合に応じた自社の給与をそれぞれ支払う想定で解説しましたが、この場合、社会保険は二以上事業所勤務の状態になる可能性が高いという点と、雇用保険はいずれか給与が高い方の被保険者にしかならないという点において、企業側、出向者側の双方に事務手続きの煩雑さや給付面でのデメリットをもたらす場合がありますので、筆者個人としてはあまりお勧めしません。
つまり、出向先で100%業務に従事する場合、出向元と出向先とで兼務する場合のいずれであっても、給与はなるべくいずれか一方のみが出向者へ一旦支払うこととし、もし当該給与を相手方も負担する必要がある場合には、出向元と出向先の会社間で調整する(金銭をやり取りする)のがよいのではないかと、筆者としては考えるところです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
〔執筆者プロフィール〕

〔この執筆者の記事〕