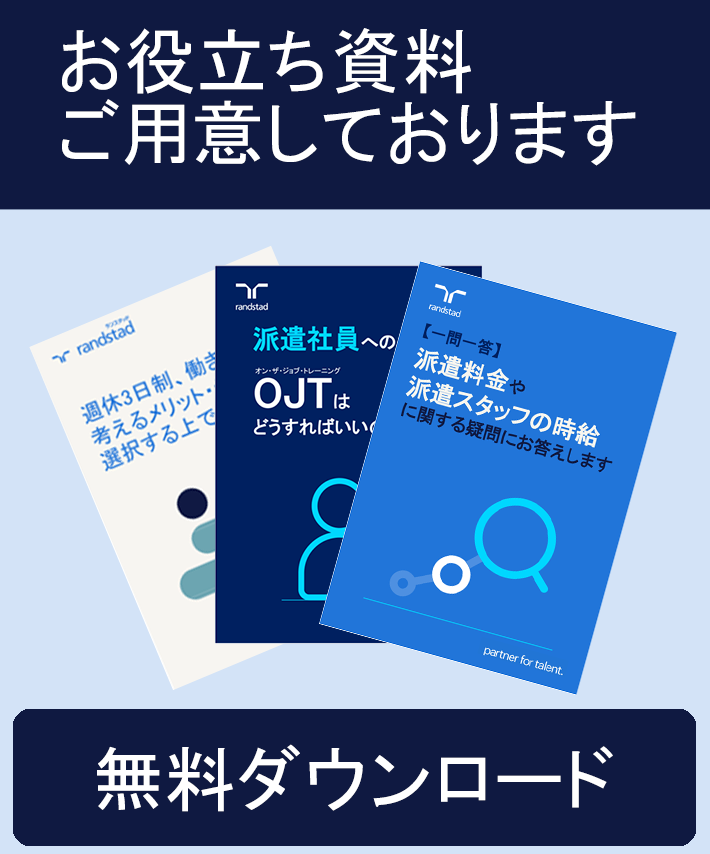- 総合人材サービス ランスタッドTOP
- 法人向けHRブログ workforce Biz
- 社労士のアドバイス/副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)
社労士のアドバイス/副業・兼業に関する留意点(中編:労働時間の通算)


こんにちは、社会保険労務士法人大野事務所の土岐と申します。社労士として、企業の皆様から寄せられる人事・労務管理に関する様々なご相談に対応させていただいております。本コラムでは、労働・社会保険諸法令および人事労務管理について、日頃の業務に携わる中で悩ましい点や疑問に感じる点などについて、社労士の視点から、法令上の観点を織り交ぜながら実務上考えられる対応等を述べさせていただきます。
さて、今回は前回に引き続き「副業・兼業に関する留意点」について、厚生労働省が公開している「副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説(以下、解説)」をベースにご紹介します。
Indexポイント労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法と簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)) (1)原則的な労働時間管理の方法 ①所定労働時間の通算 ②所定外労働時間の通算 (2)簡便な労働時間管理の方法(管理モデル) おわりに |
ポイント
|
労働時間の通算(原則的な労働時間管理の方法と簡便な労働時間管理の方法(管理モデル))
副業・兼業に際しては、雇用による場合と業務委託などの雇用によらない場合のいくつかの組み合わせが考えられますところ、以下の4パターンに区分できます。本業および副業・兼業が雇用の場合に労働基準法(以下、労基法)が適用されることから、(1)の場合にのみ、労働時間の通算が必要となります。ただし、形式上は業務委託契約であったとしても、実態が雇用契約であるとされる場合には労基法の適用となることから、結果として労働時間の通算が必要となる点には注意が必要です。
| 組み合わせ | 例 |
| (1) 本業:雇用 副業・兼業:雇用 | ・ 本業:正社員、副業・兼業:パート・アルバイト ・ 本業、副業・兼業:パート・アルバイト ・ 本業、副業・兼業:正社員 |
| (2) 本業:雇用 副業・兼業:非雇用 | ・ 本業:正社員、副業・兼業:業務委託、役員就任 |
| (3) 本業:非雇用 副業・兼業:雇用 | ・ 本業:業務委託、副業・兼業:パート・アルバイト |
| (4) 本業:非雇用 副業・兼業:非雇用 | ・ 本業:業務委託、副業・兼業:業務委託 |
さて、労基法第38条第1項では、「労働時間は、事業場を異にする場合においても、労働時間に関する規定の適用については通算する。」と規定されており、「事業場を異にする場合」とは事業主を異にする場合をも含む(労働基準局長通達(昭和23年5月14日付基発第769号))とされています。
これは、例えばある日について本業のA社において所定労働時間が8時間、副業・兼業先の所定労働時間が2時間であった場合、A社とB社の所定労働時間を合計して、当該者の労働時間は10時間と算定するということです。
ただし、上記(1)のように本業と副業・兼業のいずれも雇用の形態であったとしても、労基法は適用されるものの労働時間規制が適用されない場合(農業・畜産業・養蚕業・水産業、管理監督者・機密事務取扱者、監視・断続的労働者、高度プロフェッショナル制度)には、労働時間は通算されません。
なお、副業・兼業の促進に関するガイドライン(以下、ガイドライン)では、「これらの場合においても、過労等により業務に支障を来さないようにする観点から、その者からの申告等により就業時間を把握すること等を通じて、就業時間が長時間にならないよう配慮することが望ましい。」としている点、労働時間が通算される場合にはもちろんのこと、通算されない場合にも長時間労働とならないように配慮すべきといえます。
また、ガイドラインでは、労働時間が通算して適用される労基法の規定と、通算されない規定についても示されており、まとめると以下の通りです。
|
内容(条項) |
通算の別 |
|
|
法定労働時間(労基法第32条) |
通算される |
|
|
時 間 外 ・ 休 日 労 働 |
時間外労働と休日労働の合計で単月100時間未満、複数月平均80時間以内 |
通算される |
|
36協定により延長できる時間の限度時間 |
通算されない |
|
|
36協定に特別条項を設ける場合の1年についての延長時間の上限 |
通算されない |
|
|
それぞれの事業場における時間外労働が36協定に定めた延長時間の範囲内であるか否か(その他) |
通算されない |
|
|
休憩(労基法第34条)、休日(労基法第35条)、年次有給休暇(労基法第39条) |
通算されない |
|
それでは、ガイドラインに示されている労働時間に通算に関して、2つの通算方法について以下の通り解説します。
(1)原則的な労働時間管理の方法
所定労働時間と所定外労働時間の通算の方法については、それぞれ異なります。順を追って確認しましょう。
①所定労働時間の通算
自社の所定労働時間と副業・兼業先の所定労働時間を通算し、時間外労働に該当する部分がないかを確認します。通算の結果、自社の労働時間制度における法定労働時間を超える部分が生じた場合には、その超過部分が時間外労働となります。そして、その時間外労働については、労働契約を時間的に後から締結した企業が、自社の36協定に基づき時間外労働を行わせることになります。

【出典:厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説】
上図の具体例で確認します。
企業Aでは時間的に先に労働契約を締結し、所定労働時間は1日5時間、企業Bでは時間的に後に労働契約を締結し、所定労働時間は1日4時間の場合です。
所定労働時間の通算は、時間的に先に契約した労働契約の所定労時間(企業Aの5時間)に、時間的に後に契約した労働契約の所定労働時間(企業Bの4時間)を加えることになります(合計9時間)。1日の法定労働時間である8時間を超えることになりますところ、時間的に後に契約した企業Bの所定労働時間のうちの1時間、すなわち、(例1)では17時~18時の1時間が、(例2)では11時~12時の1時間が時間外労働になるというわけです。
②所定外労働時間の通算
自社の所定外労働時間と副業・兼業先における所定外労働時間については、当該所定外労働が行われた順に通算します。これに対し、上記①で述べた所定労働時間の通算は労働契約の締結順に従って行われるため、所定労働時間と所定外労働時間とで通算の順序に関する取扱いが異なる点に留意する必要があります。
【出典:厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説】
こちらも上図の具体例で確認してみましょう。
企業Aでは時間的に先に労働契約を締結し、所定労働時間は1日3時間(7:00~10:00)-①、当日に発生した所定外労働時間は2時間(10:00~12:00)-③、企業Bでは時間的に後に労働契約を締結し、所定労働時間は1日3時間(15:00~18:00)-②、当日に発生した所定外労働時間は1時間(18:00~19:00)-④の場合です。
次に、(例2)を確認します。
企業Aでは時間的に先に労働契約を締結し、所定労働時間は1日3時間(14:00~17:00)-①、当日に発生した所定外労働時間は2時間(17:00~19:00)-④、企業Bでは時間的に後に労働契約を締結し、所定労働時間は1日3時間(7:00~10:00)-②、当日に発生した所定外労働時間は1時間(10:00~11:00)-③の場合です。
(2)簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)
管理モデルの導入手順は以下の通りです。なお、副業・兼業を行おうとする労働者と時間的に先に労働契約を締結する使用者のことを「使用者A」、副業・兼業を行おうとする労働者と時間的に後から労働契約を締結する使用者のことを「使用者B」とします。
| ① | 副業・兼業の開始前に、次の(A)と(B)を合計した時間数が時間外労働の上限規制である単月100時間未満、複数月平均80時間以内となる範囲内において、各々の使用者の事業場における労働時間の上限をそれぞれ設定する(※1)。 (A)使用者Aの事業場における法定外労働時間 (B)使用者Bの事業場における労働時間(所定労働時間および所定外労働時間) |
| ② | 副業・兼業の開始後は、各々の使用者が①で設定した労働時間の上限の範囲内で労働させる。 |
| ③ | 使用者Aは自らの事業場における法定外労働時間の労働(※2)について、使用者Bは自らの事業場における労働時間の労働について、それぞれ自らの事業場における36 協定の延長時間の範囲内とし、割増賃金を支払う。 |
(※1)労働時間の上限をそれぞれ設定するに当たっては、当該労働者を介して各々の使用者の事業場における労働時間の上限を調整する方法のほか、使用者Aが、自らの事業場において想定される法定外労働時間を前提に、使用者Bの事業場において設定可能な労働時間の上限を算出し、その時間数の範囲内で労働時間の上限を設定するよう、当該労働者を介して使用者Bに求めるといった方法も考えられます。
(※2)使用者Aが、法定外労働時間に加え、所定外労働時間についても割増賃金を支払うこととしている場合には、使用者Aは所定外労働時間の労働について割増賃金を支払うことになります。
<管理モデルのイメージ>

【出典:厚生労働省:副業・兼業の促進に関するガイドラインわかりやすい解説】
管理モデルでは副業・兼業先の使用者Bにおける労働時間は常に時間外労働時間として取り扱う、というのがポイントです。実務上、このような取り扱いを受け入れることができるケースは少ないのかもしれませんが、特殊な知識・技能・能力を有する労働者が必要な場合にはこの方法を採用することにメリットがあるのかもしれません。解説には、管理モデルを導入した場合の労働時間の取扱いに関する通知の様式例が掲載されていますので、導入の際はご参考にしてください。
また、上記で述べた労働時間の通算方法はフレックスタイム制や1カ月単位の変形労働時間制等の労働時間制度の適用はなく、いずれも原則の労働時間制の適用を前提とした労働時間の通算の考え方となります。フレックスタイム制等の原則の労働時間制以外の場合の労働時間通算の考え方に関しては、厚生労働省のQ&Aで述べられておりますので、詳細はこちらをご参照ください。
![]()
おわりに
副業・兼業時の労働時間の通算方法については以上の通りです。
実務を考えますと非常に煩雑であると言わざるを得ませんが、現在、厚生労働省の専門部会(労働条件分科会)では、副業・兼業時の労働時間の通算および割増賃金の仕組みの見直しの要否について検討されています。
労働者側からは「副業・兼業時の労働時間通算、割増賃金規制の遵守・徹底を行っていくべき」、「割増賃金が実際に支払われていないのであれば、ルールを緩和するのではなく、ガイドラインを含め、現行ルールを一層周知し、適正運用を広げるような取組を進めるべき。」といった意見が述べられています。
一方、使用者側からは「割増賃金規制によってその普及が阻害されており、健康確保のための労働時間通算規制を残すことを前提に見直しを図ることが必要。」、「副業は、会社の業務命令ではなく、労働者本人が選択して就労するのだから、労働時間を通算して割増賃金を支払うことは違和感があり、割増賃金規制の趣旨にもなじまない。」といった意見が述べられています。
今後の副業・兼業時の労働時間の通算および割増賃金の支払いについて見直される可能性がありますが、本コラム執筆時点(2025年10月)では以上の通りです。
最後までお読みいただきありがとうございました。

23歳のときに地元千葉の社労士事務所にて社労士業務の基礎を学び、2009年に社会保険労務士法人大野事務所に入所しました。現在は主に人事・労務に関する相談業務に従事しています。お客様のご相談には法令等の解釈を踏まえたうえで、お客様それぞれに合った適切な運用ができるようなアドバイスを常に心がけております。