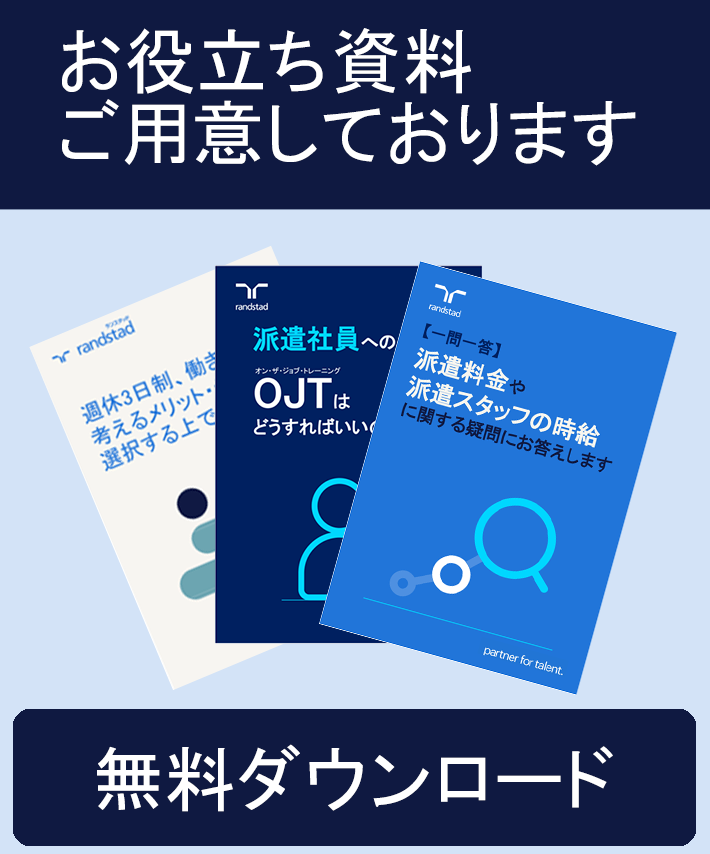- 総合人材サービス ランスタッドTOP
- 法人向けHRブログ workforce Biz
- 社労士のアドバイス/フレックスタイム制の導入のポイントと運用上の留意点(後編)
社労士のアドバイス/フレックスタイム制の導入のポイントと運用上の留意点(後編)


こんにちは、社会保険労務士法人大野事務所の土岐と申します。社労士として、企業の皆様から寄せられる人事・労務管理に関する様々なご相談に対応させていただいております。本コラムでは、労働・社会保険諸法令および人事労務管理について、日頃の業務に携わる中で悩ましい点や疑問に感じる点などについて、社労士の視点から、法令上の観点を織り交ぜながら実務上考えられる対応等を述べさせていただきます。
さて、前回に引き続き「フレックスタイム制に関する基本的なルールと運用上の留意点」について採り上げます。なお、今回も清算期間は1か月とする前提において解説します。
Index①年次有給休暇の取扱い
②半休制度の適用と取り扱い
③時間単位年休制度の適用と取り扱い
①遅刻・早退、欠勤の取り扱い
②規律保持対策として考えられること
①朝礼の参加を強制できるか
②時刻指定のある重要な業務命令・時間外労働命令の是非
③フレックスタイム制における使用者の労働時間把握義務
④年休の出勤率の算定
⑤出向社員、派遣社員へのフレックスタイム制の適用は
|
ポイント
|
1. 年次有給休暇
①年次有給休暇の取扱い
年次有給休暇(以下、年休)を取得した日については、「標準となる1日の労働時間」(以下【図】の(B))について労働したものとみなして労働時間を清算することになりますが、このとき、この「みなし労働時間」(同(B))を含めることによって労働時間が「法定労働時間の総枠」(同(C))を超える場合に、法定の割増賃金を支払う必要があるか否かの疑問が生じます。
この点、労働基準法(以下、労基法)では実際に働いた時間をカウントする実働時間主義に基づくため、「みなし労働時間」(同(B))を含めない実働時間(同(D))が「法定労働時間の総枠」(同(C))を超えない場合には、法定の割増賃金(時間単価×0.25)を支払う必要はありません。しかし、この場合でも「清算期間における総労働時間(所定労働時間)(同(A))」を超える場合には、その時間分の賃金(時間単価×1.0)の支払いは必要となる点は注意が必要です。
このように、割増賃金の清算において「みなし労働時間」(同(B))は実働時間(同(D))と区別して考えられますが、実務上は割増率ごとに時間を集計することは非常に煩雑となりますので、就業規則等において「清算期間における総労働時間(所定労働時間)」(同(A))を超えるところから、一律に法定の割増賃金を支払うこととしているケースが多く見受けられます。
なお、36協定に定める時間外労働の上限との関係においても、実働時間主義に基づき、「みなし労働時間」(同(B))は含めない実働時間をその対象としてカウントすることになります。

②半休制度の適用と取り扱い
半日単位による年休(以下、半休)について、行政通達(平7.7.27基監発33)では「労働者がその取得を希望して時季を指定し、使用者が同意した場合であり、かつ、本来の取得方法による年次有給休暇の阻害とならない範囲内で運用される限りにおいては、むしろ年次有給休暇の取得促進に資するもの」としており、フレックスタイム制の下でも同様に半日単位による年休付与も問題ないものと考えられます。
なお、この場合の労働時間の算定に当たっては、労使協定で定めた「標準となる1日の労働時間」の2分の1の労働時間について労働したものとみなす時間とするのが妥当でしょう。
ただし、フレックスタイム制においては始業および終業の時刻を労働者に委ねるという特性上、半休の取得に関しては一定の取得ルールを設けておくことをお勧めします。
例えば、コアタイムを設けている場合でコアタイム全てを就労したとしても半休を認めるケースを考えてみますと、フレキシブルタイムは必ずしも就労せずともよいことになりますから、半休をもって1日の休暇を取得できてしまうことになります。このような取得とならないよう、「コアタイムの一部を就業する場合にのみ取得可能」といった定めが考えられます。
また、完全フレックスタイム制の場合、コアタイムの設定がないことにより就業する時間帯が特定されていないということになりますので、フレキシブルタイム中の全ての時間について半休を取得する余地が生じます。
すでに1日の標準労働時間を労働した場合であっても、半休を取得できてしまうことになりますところ、こうしたケースに対応するために、例えば「半休は当日の実働時間が4時間以下の場合にのみ取得可能」といった定めをしておくことが考えられます。
③時間単位年休制度の適用と取り扱い
2010年の労基法改正により、年休の取得率向上を目的として、労使協定を締結することで、付与日数のうち5日を上限として時間単位による年休(以下、時間単位年休)を付与することが可能となりました。これに関連して、フレックスタイム制を適用している事業場においても時間単位年休を導入できるかの疑問が生じます。
この点について、導入できないとする法的根拠はなく、労使協定を締結することで時間単位年休制度の導入は可能と考えられます。労使協定においては「時間単位年休1日分に相当する時間数(1時間に満たない端数は切り上げ)」を定める必要がありますが、これは1日の年休を時間単位に換算すると何時間分となるかを定めるもので、フレックスタイム制では「標準となる1日の労働時間」とするのが妥当と考えられます。
次に、上記②の半休制度と同様に運用面を考慮し、時間単位での取得が可能な対象時間帯をあらかじめ明確に定めておくことが重要です。例えば労働義務のあるコアタイムのみを対象とする場合や、「標準となる1日の労働時間」までを対象とする場合などが考えられます。
また、清算期間の終了直前に、不就労時間の調整を目的として時間単位の年休をまとめて取得するケースも想定されますが、これはリフレッシュを目的とする年休本来の趣旨に反するおそれがあるといえますので、「事前に申請を行うこと」や「事後に不就労時間と相殺することはできない」といった取り決めを設けておくことが望ましいといえるでしょう。
![]()
2.遅刻・早退、欠勤
①遅刻・早退、欠勤の取り扱い
フレックスタイム制では1日や1週間単位の所定労働時間という概念が存在しません。このため、清算期間内に所定の総労働時間を満たしている限り、フレキシブルタイム内での出退勤については「遅刻」や「早退」といった概念は生じません。
ただし、勤務が義務付けられているコアタイムを設定している場合には、その時間帯に遅れて出勤したり、早く退勤したりすることについて、「遅刻」「早退」という考え方は生じ得ます。もっとも、この場合であっても、清算期間内に所定の総労働時間を満たしている限り、日ごとの不就労時間について「不就労控除」を行うことはできません。
また、「欠勤」についても清算期間の総労働時間を満たしている限りにおいては、本給を日割りで控除する、いわゆる「欠勤控除」を行うことは認められません。ただし、フレックスタイム制は、所定労働日に出勤するか否かまでをも労働者の自由に委ねるものではないため、所定労働日に欠勤した場合には、勤怠記録上「欠勤」として取り扱うことになります。そのうえで、たとえば精皆勤手当の不支給といった運用を行うことは差し支えありません。
②規律保持対策として考えられること
コアタイム中の遅刻や早退、あるいは欠勤があっても特にペナルティがない、という運用になってしまうと、「そもそもコアタイムを設けている意味は?」という疑問が生じかねません。
そこで、出勤が求められているコアタイムに何らかの欠務があった場合には、それを勤怠上「遅刻」・「早退」・「欠勤」として記録し、たとえば精皆勤手当を支給しない、勤怠に対する評価として賞与や昇給の査定に影響させる、といった対応をすることが公平性や職場の基本的な規律を保つ観点からも有効と考えられます。
フレックスタイム制は柔軟で働きやすい仕組みですが、一方でルーズにならないための一定のルール設定も、円滑な運用のカギになるといえるでしょう。
![]()
3.その他
①朝礼の参加を強制できるか
フレックスタイム制は始業および終業時刻のいずれも労働者自身が決められるという点がポイントです。つまり、始業か終業のどちらか一方だけが自由という場合は、正式な意味でのフレックスタイム制とはいえない点については、以前のコラムでも触れた通りです。
たとえば、毎朝全員が集まって朝礼を行うことが義務づけられているような職場では、実質的に始業時刻が固定されていることになります。このようなケースでは、「社員が始業時刻を自分で決めている」とは言えませんから、制度上はフレックスタイム制とは認められないことになります。
②時刻指定のある重要な業務命令・時間外労働命令の是非
フレックスタイム制を導入している職場でも、たとえば時刻が決まっている重要な会議や打ち合わせなど、どうしてもその時間に出勤してもらわなければ業務が回らないといった場面は現実にはあると思います。このような「特別な勤務要請」を、果たしてフレックスタイム制の対象となっている労働者にも行うことができるのか?というのは、実務上たびたび議論になるところです。
たしかに、フレックスタイム制のもとでは、基本的に会社(使用者)は、各日の始業や終業の時刻を一方的に指示することはできないとされています。しかし、この制度の背景には、「労働時間の自主的な決定」は、あくまで業務との調和を前提とするという考え方があります。つまり、会社側にも勝手な命令はできませんが、労働者側にも「業務に支障が出ないように配慮する責任」があるといえます。
したがって、やむを得ない業務上の必要があるにもかかわらず、「その時間はプライベートを優先したいから」といった理由で正当な要請を拒み続けるようでは、労働契約上負うとされている誠実勤務義務(労働契約法第3条第4項)を果たしているとは言いがたいものです。そうしたケースでは、評価や査定において相当の考慮をする可能性や必要性は充分にあるといえるでしょう。
③フレックスタイム制における使用者の労働時間把握義務
フレックスタイム制を導入している職場でも、使用者には「労働時間を適切に把握・管理する義務」があります。この点、通達(昭63.3.14基発150・婦発47)に「フレックスタイム制を採用する事業場においても、各労働者の各日の労働時間の把握をきちんと行うこと」と明記されている通りです。
しかしながら、フレックスタイム制では始業および終業の時刻を労働者が自由に決定できるため、会社がすべての勤務実態を逐一把握するのは難しい側面があるのは事実といえるでしょう。特に労働時間の記録を自己申告制にしている場合、どうしても実態とずれた過大申告や過少申告が発生しやすく、上長もそのズレに気づきにくいのが現実です。
そのため、自己申告制を採用する場合には、「正しく申告することの大切さ」を日頃から繰り返し伝えることが大切です。また、上長も「申告された内容が妥当かどうか」を定期的に確認し、必要に応じて声かけを行うなどの対応が求められます。
④年休の出勤率の算定
年休の付与にあたっては、「全労働日の8割以上を出勤していること」が一つの要件となりますところ、この出勤率の算定に関して、フレックスタイム制を導入している場合でも、基本的な考え方は変わりません。
例えば、ある日にコアタイムをすべて欠勤し、フレキシブルタイムに一部だけ勤務したようなケースであっても、出勤率は「労働日単位」で判断することとされているため、その日は「出勤日」として取り扱わなければなりません。
⑤出向社員、派遣社員へのフレックスタイム制の適用は
最後に、フレックスタイム制を適用している事業場において、出向社員や派遣社員についても、社員と同様にフレックスタイム制を適用できるのかという点は以下の通りとなります。
| (ⅰ)出向社員 | 在籍出向では出向先でも雇用契約関係を発生させることになるので、出向先の就業規則、労使協定等にフレックスタイム制が規定されていれば、これによりフレックスタイム制の対象とすることが可能。 |
| (ⅱ)派遣社員 |
労働者派遣の場合、派遣先会社と派遣社員には雇用関係が発生しないため、派遣元会社の就業規則、労使協定等にフレックスタイム制が適用されている必要がある。
また、派遣元会社と派遣先会社との派遣契約において、派遣社員をフレックスタイム制の下で就業させる旨を定めるといった手順を踏めば、フレックスタイム制を適用することが可能。
|
![]()
まとめ
以上、3回にわたってフレックスタイム制について述べました。フレックスタイム制は一見便利な制度といえますが、一方で労働時間の管理や半休および時間単位年休の取得に関しては事前にルールを定めておくべきポイントがあります。
労使双方にとってフレックスタイム制の適用に疑義が生じないよう、基本的なルールと運用時の留意点については押さえておきたいところです。
最後までお読みいただきありがとうございました。
<参考URL>
■厚生労働省 フレックスタイム制のわかりやすい解説&導入の手引き