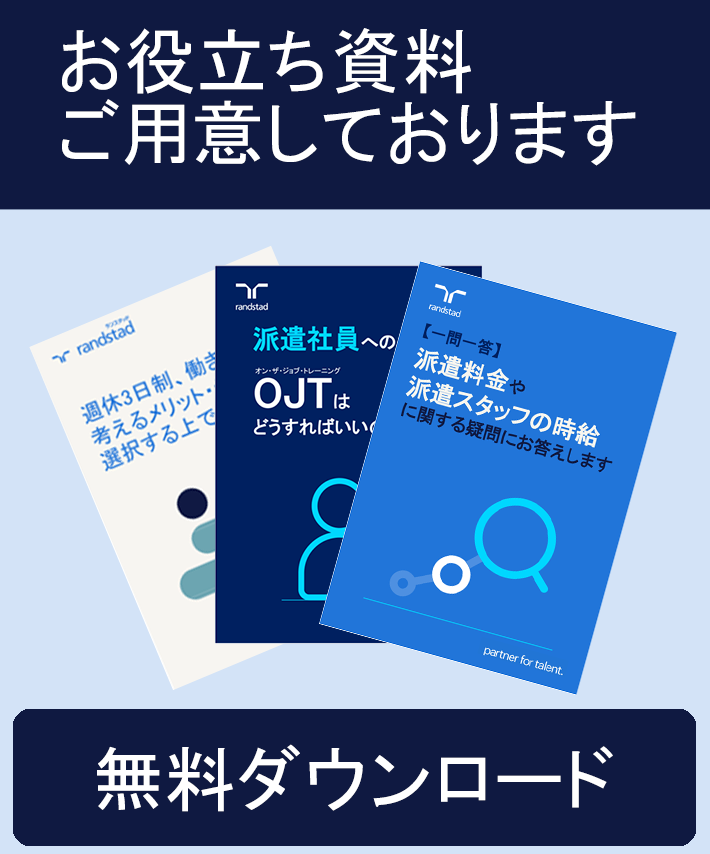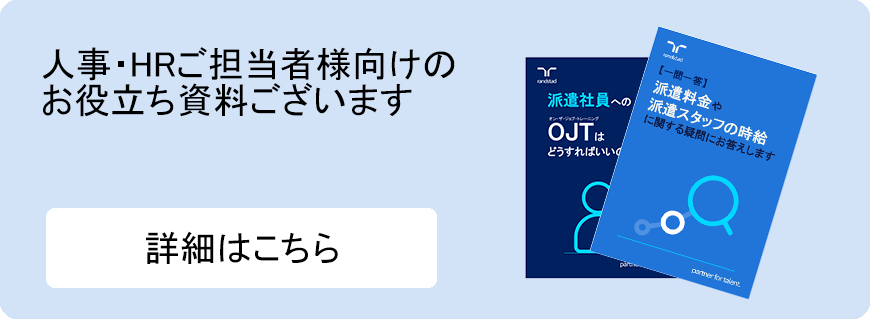- 総合人材サービス ランスタッドTOP
- 法人向けHRブログ workforce Biz
- 【採用担当者必見】リファレンスチェックで「採用の成功率」を劇的に高める質問戦略
【採用担当者必見】リファレンスチェックで「採用の成功率」を劇的に高める質問戦略


多くの企業が主要ポジションの採用に際してリファレンス(推薦者)を求めていますが、残念ながら、その価値を最大限に引き出せているケースは少数です。型通りの質問では、「良い人でした」「問題ありません」といった漠然としたポジティブな意見と、基本的な勤務情報の確認に終始してしまいがちです。
質問の質を高めることで、リファレンスチェックは、
- 候補者の核となる強み
- 克服すべき潜在的な課題
- あなたの組織とのカルチャーフィットの度合い
を浮き彫りにする強力なツールに変わります。
この背景情報があれば、入社後のオンボーディングをスムーズに進められるだけでなく、ミスマッチによる早期離職という高額なコストと生産性へのダメージを防ぐことができます。
本記事では、リファレンスチェックを最大限に活用し、「聞くべきこと」を明確にするための具体的なステップを解説します。そして、すぐに使える質問リストが必要な方は、記事の最後でテンプレートを無料ダウンロードできますので、ぜひご活用ください。
ステップ1:基本情報の「裏取り」を徹底する
リファレンス担当者との貴重な対話時間で、基本的な事実確認に時間を費やすのはもったいないと感じるかもしれません。しかし、「勤務期間」「役職」「業務内容」「習得スキル」といった基本情報の確認は、リファレンスチェックにおいて最も重要な要素の一つです。
これらの事実は、候補者の人柄を教えてくれるわけではありませんが、コアコンピテンシーに関する自己申告の真実性を担保します。
キャリアに関する各種調査によると、日本ではもちろん、グローバルでも7割近い人が履歴書や職務経歴書に何らかの「虚偽」を記載した経験があるというデータもあります。採用担当者の4人のうち3人が、レジュメの嘘を見抜いた経験がある[1]という報告もあるほどです。
つまり、基本情報の二重チェックは、「採用しようとしている人物が、彼らが主張する通りの優秀な候補者であるか」を素早く、かつ確実に検証するために欠かせないプロセスなのです。

ステップ2:質問は「具体的」かつ「オープンエンド」に設計する
必要な情報を得るために、どのような質問をすれば良いか悩むかもしれません。「彼(彼女)と一緒に働くのはどんな感じでしたか?」というような漠然とした質問では、一般的な背景しか得られず、具体的な回答は引き出せません。
重要なのは、質問の焦点を絞ることです。
例えば、「期日(デッドライン)に対するコミットメントはどの程度でしたか?」や、「もし機会があれば、再度この候補者を雇用したいと思いますか?」といった質問が有効です。
これらの質問が良い例とされるのは、具体的でありながらオープンエンド(自由回答形式)な要素も持っているからです。リファレンス担当者は、焦点を絞った質問によって関連性の高い具体的な情報[2]を提供しやすくなります。同時に、答えに広がりを持たせることで、想定外の興味深い洞察を引き出すきっかけにもなります。
ステップ3:「カルチャーフィット」の可能性を明確に評価する
候補者があなたの会社の企業文化(カルチャー)に馴染むかどうかは、履歴書を読むだけでは判断が難しい、非常に重要な問題です。面接を重ねても、実際に採用してみるまで推測の域を出ないことも多いでしょう。
リファレンスチェックは、このカルチャーフィットの可能性を明確にし、評価するための絶好の機会です。
「前職での同僚との働き方」「前職の文化の特徴」「その文化で候補者がどのように活躍していたか」といった情報を詳しく聞くことで、長期的にあなたの組織で活躍できるかについて、十分な情報に基づいた予測を立てることができます。
現代において、新しい従業員を採用するコストは上昇し続けています。そして、多くのビジネスパーソンが「カルチャーミスマッチ」[3]が原因で離職した経験があると答えています。カルチャーへの適合性を確認することは、金銭的なコストと、関係者へのストレスの両方を節約することにつながるのです。
ステップ4:聞いてはいけないことを把握し、個人情報保護法を遵守する
リファレンスチェックで収集する情報も、他の個人情報と同様に「個人情報保護法」や各国のプライバシー規制の対象となります。そのため、取得するデータの種類には細心の注意が必要です。
採用候補者の雇用履歴や過去のパフォーマンスに関する質問は、正当な理由があるため個人情報の収集が認められやすい領域です。しかし、欠勤記録やプライベートな生活に関する質問には注意が必要です。
「病歴や障害」「性的指向」「信教」などといった、機微情報(センシティブデータ)[4]に該当する情報をリファレンス担当者がうっかり開示してしまうリスクがあるからです。こうした機微情報の保存には厳しい規制があり、多くの企業は正当な理由を持っていません。
機微情報を引き出す可能性のある質問は避け、万が一、誤って入手してしまった場合は、直ちに削除するなど、法規制の遵守を徹底してください。
ステップ5:リファレンスから応答が得られない場合の対策
業界や国によっては、リファレンスの提供が法的に義務付けられている場合もありますが、多くの企業にとってそれは任意です。
リファレンスの提供を拒否する企業[5]もあります。これは、対応に時間をかけたくないという理由や、不満を持つ元従業員からの訴訟リスクを恐れているためです。中には、「氏名、在籍期間、役職」といった基本的な情報のみを人事部門の定型文として提供するケースもあります。
このような場合でも、元雇用主の対応の悪さ[6]を候補者の評価にネガティブに反映させてはなりません。彼らがリファレンスの提供を渋るのは、必ずしも問題の兆候(レッドフラグ)ではないからです。
候補者と状況について話し合い、代替となる適切なリファレンスを探すための時間を与えましょう。
まとめ:あなたの採用プロセスをアップグレードする
今回ご紹介したポイントが、次回の採用時にリファレンスチェックの質問を考える際の参考になれば幸いです。
さらに詳しくサポートしたい方には、リファレンスチェック用質問テンプレートをご用意しています。Word形式で、すぐに使える形になっており、27の基本的かつ実践的な質問例と、候補者やリファレンスの情報を記入できるメモ欄が含まれています。
採用プロセスで活用しながら、必要に応じて質問をカスタマイズしていただくことも可能です。ぜひ次回のチェックに役立ててみてください。
[出典・参考資料]
本記事は以下の情報を参考に作成しました。
[1] 就職のための嘘の真実【2023年データ】より
[2] 誰かの推薦状を確認する正しい方法 より
[3] 企業文化が合わないと4人中3人が退職する より
[4] どのような個人データが機密とみなされますか? より
[5] 参考資料: あなたの権利 より
[6] 雇用主からの否定的な推薦を受けた従業員の権利より