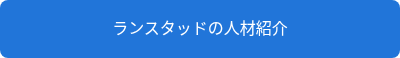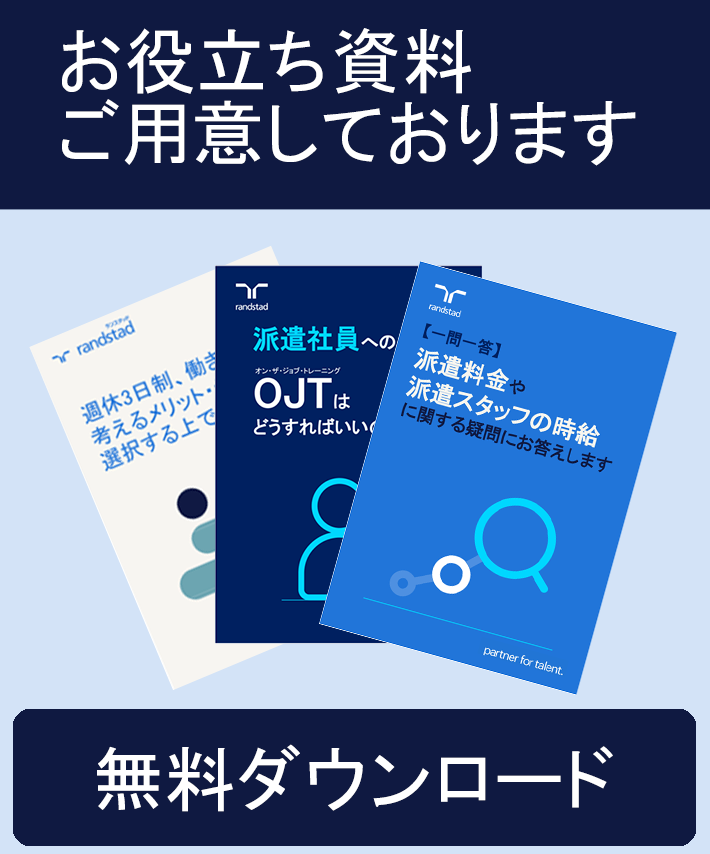- 総合人材サービス ランスタッドTOP
- 法人向けHRブログ workforce Biz
- AI活用で先行する製薬業界に学ぶ、テクノロジーと「人」を両立させる方法
AI活用で先行する製薬業界に学ぶ、テクノロジーと「人」を両立させる方法


創薬などAI活用で世界をリードするライフサイエンス・製薬業界。しかし人材戦略では?
生成AIの活用により、ライフサイエンス・製薬業界では創薬や診断・治療法の創出などが加速しています。生成AIはライフサイエンス・製薬業界に年間最大1,100億ドルの価値をもたらす可能性があるとのデータもあります。
ランスタッドは、世界の経営幹部および人事部門のリーダー1,060名を対象としたグローバル調査「2025年 タレントトレンドレポート ライフサイエンス・製薬業界版」を公開。同調査によると、ライフサイエンス・製薬業界の多くの企業がこの波に乗ろうとする中、ある矛盾した実態を抱えていることが明らかになりました。同業界は「ある分野ではAI活用で他業界を圧倒的にリードしている」一方で、「組織の根幹をなす人材戦略においては深刻な課題を抱えている」という傾向が見られるのです。
このギャップこそが、ライフサイエンス・製薬業界の今後の成長を左右する大きな分岐点かもしれません。本記事では、グローバル調査を元にした他業界との比較から、日本のライフサイエンス・製薬業界が直面する独自の課題と、未来をリードするための次の一手を探ります。
ライフサイエンス・製薬業界の強みとは?スキル特定と自動化で他業界を圧倒
強み①:AIによる従業員のスキル・潜在能力の特定
同調査によると、ライフサイエンス・製薬業界の59%の企業が、「AIを活用して従業員のスキルや潜在能力を特定し、社内異動の機会につなげている」と回答しています。これは全業界の中で最も高い数値であり、世界平均(46%)を大きく上回っています。
強み②:業務への積極的なAI活用
同調査では、88%もの企業が「AIによって従業員はより価値の高い仕事に集中できる」と回答。これも主要業界の中で最も高い水準であり、AIをポジティブに捉え、活用しようという意欲の高さがうかがえます。
これらのデータは、ライフサイエンス・製薬業界が「個々の人材の能力を見抜き、適材適所に配置する」という点において、AIの積極的な活用による非常に高いポテンシャルを秘めていることを示唆しています。
![]()
浮き彫りになる「人材戦略」でのボトルネック
課題①:学習・開発(L&D)投資の遅れ
同調査では「学習・開発(L&D)への投資を増やす」と回答した企業はわずか37%に留まりました。これは世界平均(53%)を16ポイントも下回る数値です。従業員の育成や能力開発に消極的な企業の姿勢は、成長意欲のある優秀な従業員のエンゲージメント低下につながりかねません。
課題②:人事部門のスキルアップ機会の不足
人事部門向けの研修を優先している企業は39%に留まり、これも世界平均(50%)に大きく水をあけられています。専門性の高い業界だけに、バックオフィスよりも主事業のスキルアップを優先せざるを得ない背景もあるかもしれません。しかし、AI時代の新たな人材戦略を設計し、全社に展開していくのは人事部門自身であり、同部門のスキルアップは優秀な人材の確保につながる重要な取り組みといえます。

課題③:スキルベースの考え方が受け入れられにくい硬直的な状況
「現場の管理職が、経歴や特定の職務に固執し、スキルベースの考え方を受け入れていない」と感じる人事部門のリーダーは43%にものぼり、主要業界で最も高い割合となっています。ライフサイエンス・製薬業界が好調であるがゆえに、現時点では従来通りでも課題を感じにくいのかもしれません。しかし、こうした硬直的な状況が、将来につながる学習・開発(L&D)や人事スキルの課題となる可能性は想像に難くありません。

「人材個々のスキルを見抜く力」は高く、AI活用も順調に進んでいるというのに、なぜ依然として「組織として人材を育て、活かす仕組み」が追いついていないのでしょうか。
このギャップがもたらすリスクは、ランスタッドが世界の働く人々を対象に行った意識調査「ワークモニター2025」の結果を見ると、より鮮明になります。この調査では、実に44%の労働者が「将来に役立つスキルを身につける機会がなければ仕事を受け入れない」と回答しており、昨年の36%から上昇しています。
企業側の学習・開発(L&D)投資の遅れと、成長を渇望する従業員との意識の乖離。企業の方針と従業員の期待との間に生まれたこのギャップが、タレントマネジメントにおける見過ごせない課題であることを物語っています。
![]()
【コンサルタントの視点】データが示す"ギャップ"を乗り越える方法
データで明らかになったライフサイエンス・製薬業界特有の「光と影」。この現状について、現場の最前線に立つランスタッド プロフェッショナルタレントソリューション事業本部 第1営業部 ライフサイエンスチームマネージャー 山川司は、より具体的に課題を指摘し、解決への道筋を示しています。
「本レポートは、ライフサイエンス・製薬業界が直面する『AI活用の加速』と『専門人材不足』という2つの大きな課題を指摘しています。昨今の業界全体の求人数は増えていませんが、バイオインフォマティクスや細胞・遺伝子治療など先端分野では競争が激化し、AI人材の需要も急拡大しています。しかし業界内のAIスキルを持つ人材は限られており、異業種からの採用に注力しているのが実情です」。
山川が指摘するように、特に先端分野における専門人材の獲得競争は激化の一途をたどっています。そして、こうした状況で企業が勝ち抜くためには、従来の人材戦略からの脱却が不可欠であると山川は続けます。
「従来の経歴重視型では変化に追随できず、『スキル・ファースト』と『アジャイル』な労働力設計が不可欠となります。外部人材の確保と同時に社内リスキリングを強化し、柔軟な組織体制を築く必要があります」。
この「スキル・ファースト」や「アジャイル」な労働力設計は、まさにIT業界などが先行して取り組んでいる戦略です。では、ライフサイエンス・製薬業界がこれを取り入れ、柔軟な組織体制を実現するためには、具体的に何が必要なのでしょうか。
「その実現には、AIを活用しスキルを可視化し、必要なプロジェクトに最適な人材を迅速に配置できる仕組み(タレントマーケットプレイス)が社内外の人材流動性を高める鍵となります」。
強みである「AIによるスキル特定能力」を、採用や育成、配置といった人材戦略全体に展開していくこと。つまりタレントマーケットプレイスの確立が、専門家の示す具体的な方法なのです。
![]()
「2025年 タレントトレンドレポート」で、自社の"現在地"と"未来"を描く
AI活用で世界をリードするポテンシャルを持ちながらも、硬直的になりがちな人材戦略が足かせとなっている。これが、今のライフサイエンス・製薬業界の姿といえます。この"ギャップ"を解消し、「スキル・ファースト」と「アジャイルな組織」へと変革していくことが、未来を切り拓くことにつながります。
本レポートには、この変革を推進するためのトレンドに関するデータと、具体的なアクションのヒントが掲載されています。自社の強みと課題を客観的に把握し、次の一手を見つけるための羅針盤として、ぜひご活用ください。